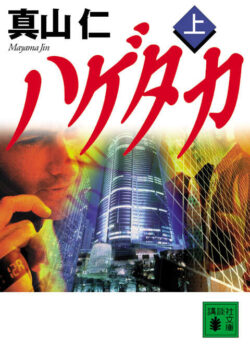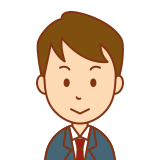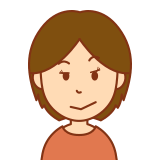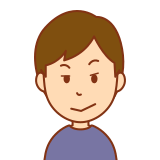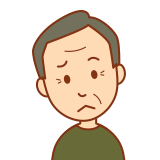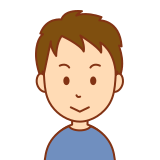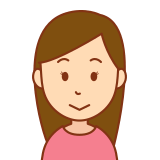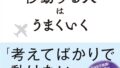Golden Weekに突入しました。飛び石ではありますが、長い休暇を取って旅行に出かける方、近場で家族と過ごす方、普段読めなかった書籍を集中して読み切る方、いろいろな過ごし方があると思います。私も、読みたいと買いためている小説などを、腰を落ち着けて読もうかなと考えています。
私が読書をするのは、自分が暮らす毎日と違う、非日常を経験したい、というのも、大きな目的の1つにあります。人間に与えられた時間1日24時間は誰もが平等、それに自分が生きるであろう年月が自分に与えられた一生の時間になるわけですが、これも長い短いはあれど考え方は誰もが平等。分身の術でも持たない限り(そのうち、AIが脳波と繋がっていくつもの生活を同時に体験することができるようになるかもしれませんが…)、自分が過ごす毎日が日常になるわけですが、もっともっと色々な人生を体験してみたい。。。だから非日常を体験できるような小説を、私は好んで読んでいます。
このブログは、リーダーシップの心技体を高める気付きを共有する場ですので、そうした小説の中から、リーダーシップを鍛えることができたと思う書籍を今日はご紹介したいと思います。
真山仁さん著作の『ハゲタカ』です。
ドラマや映画化されているので、ご存じの方も多いと思います。本著は、バブル崩壊後の不良債権処理や企業買収をめぐるディールを通じて、技術的・心理的なかけひきをダイナミックに描いた作品です。主人公の鷲津政彦は、外資系投資ファンド「ホライズン・キャピタル」の代表の1人で、ニューヨークで「ゴールデン・イーグル(イヌワシ)」と異名をとるほどの凄腕、本作は日本にて不良債権処理や企業買収を行いながらも、世界に乗り遅れつつある日本の社会構造、企業の在り方に一石を投じる、重厚なテーマを持った作品で、私の大好きな書籍の1つです。
その中で、リーダーとして身に着けておくべきだな、と思った下りを紹介したいと思います。
まずは、ビジネスに対する姿勢です。
「いいか、アラン。これだけは肝に銘じておけ.ビジネスで失敗する最大の原因は、人だ.味方には、その人がこの闘いの主役だと思わせ、敵には、こんな相手と闘って自分は何て不幸なんだと思わせることだ.そして、牙や爪は絶対に見せない.そこまで細心の注意を払っても、時として人の気まぐれや変心、あるいはハプニングのせいで、不測の事態が起きるんだ.だから、結果を焦るな.そして、馴れ合うな、いいな.」
「アラン、あなたは結局ゴールドバーグでまともに仕事をする前に、政彦のところに来たから分からないでしょうけれど、そういう配慮には、日本人もアメリカ人もないわ.自己主張と自意識過剰の塊ばかりが集まっているアメリカのインベストメント・バンクなんて、妬みと嫉妬で、優秀な連中がどんどん潰されていくんだから.実力があって結果を出せれば、手続きはどうでもいいなんて思ったら、あなたも痛い目に遭うわよ」・・・
「アメリカ人の悪いクセは、世界で一番優秀なのはアメリカ人だと信じて疑わないことだ。その結果、多くのアメリカ人は日本でのビジネスに失敗する.彼らの行動規範に「郷に入れば、郷に従え」という言葉はなかった。すべてがアメリカ流であり、それが通じなければ、あらゆる手を使ってねじ伏せにかかる。だが、それでは複雑怪奇な日本という島国では成功できない.」
もっと数字と論理構造を突き詰めることで、買収交渉を有利に進めるのかと思いきや、「ヒト」を重視する。最後はヒト。。。というのはよく耳にする言葉ではないかと思うのですが、どこの世界でもそうだと(これが真実だとするとですが)。特に、AIによって左脳部分の仕事を瞬時に完遂されるようになると、人に関わる部分こそ、もっともっと突き詰めなくてはいけない部分なのだ、と改めて認識させられます。
とはいえ、こうしたディールでは、裏の裏まで情報収集、情報の大切さも再認識させられます。
「企業買収とは一種の闘いみたいなものです.孫子の兵法ではないですが、『敵を知り、己を知らば、百戦危うからず』です.彼らの弱点、攻めどころ、さらに交渉カード、それらを知りたいという意味では、非常に有意義な面談でした.」
「金髪の外資系金融マンだと思って彼らを侮ってはいけない.芝野は背筋が寒くなるのを感じながら、そう心に刻んだ.彼らはただ漫然と与えられた資料だけで案件を査定したわけではなかったのだ.芝野は、バルクセールの買い手の投資ファンドのトップが品の良い日本であり、担当者も日本語を話せる知的な外国人だったことで、当初ホッとした自分の甘さを悔やんだ.」
「彼はああ見えて、日本の不動産の裏の裏まで知り尽くしている.三葉から出てきた赤坂や六本木の物件を一瞥するだけで、『筋が悪そうですな』と見抜き、ちゃんと自分の足で、その『筋の悪さ』を確かめてくれた.だからアランが、そう指摘した段階で、彼らは安値について何も言えなくなったんだ.」
企業活動は、依然として競争の側面が大きいですから、その競争に勝つためには、とにかく現場で情報を収集し、事象に関する感度を高くして、認知し、自らのインサイトまで昇華する。すでに公開された情報は一瞬でAIが拾ってきますので、今後ますます一次情報を求め、それを観察し、気付き、咀嚼する。こうした感度をぴかぴかに磨き上げないといけないのでしょう。
そして、最後は、私が大好きなフレーズです。
「なあ、芝野。お前、商売の鉄則を忘れてへんか」
「商売の鉄則、ですか・・・・」
「せや、ルールを決める方が主導権を握る.こっちが劣勢やったら、ルールを変えることや.」
そうなんです!
ルールを守る側ではなく、ルールを決める側に位置する。これこそが競争を有利に進める鉄則なのですね。
リーダーとしての『技』と『心』―心構えの部分では、知っておいていいことなのではないかなと思います。