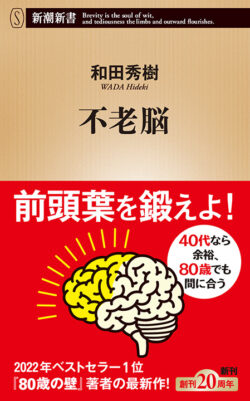私も50代に入り、ここ数年、人の名前が覚えられない、思い出せない、思い出したとしても微妙に間違っている。。。ということが増えてきました。”これは、年取ってきたか、痴呆症の兆候か。。。” と不安になったりもします。それ以外にも、脳の使い方によって、創造力や情報の処理、そもそもどうやったらフレッシュな状態で元気に脳に働いてもらえるか、など、脳の働きについての興味も尽きないところです。
そもそも、健全な心と身体がなければ、健全なリーダーシップを発揮することはできない。では、健全な心と身体を保つためには、それらを司る脳そのものの健全性を保つことが大切であり、だからこそ脳の役割や働きを知っておく必要がある。ということで、いろいろな書籍に触れたりしています。
そこで、今日は、和田 秀樹さんの、『不老脳』をご紹介します。
こちらの書籍は、加齢とともに脳も退化していくわけですが、少しでも若々しい脳を維持するためには、前頭葉が大切で、その前頭葉をどうやって維持するか、について書かれています。そちらから、興味深い点をご紹介していきます。
前頭葉が、そもそもなぜ大切なのか?
前頭葉には言葉を操る、情報を処理する、感情を制御する、運動機能をコントロールするといったその人の「人間らしさ」そのものを司る役割がありますが、そうした「自分らしさ」を発揮できるのも意欲あってこそ。ここが衰えてしまっては、あなたの創造性も粘る強さも宝の持ち腐れです。
わたしが疑っているのは「今の日本人は前頭葉が衰えているのではないか」ということです。
では、前頭葉は、どんな働きをするのでしょうか?
そもそも、前頭葉とはどんな役割を持っているのでしょうか。人の脳というのは一般的な成人で体重の約2%、約2~1.6キログラム程度の重さがあり、大脳、間脳、小脳、延髄、脊髄などの部位に分けられます。前頭葉というのは大脳の前方にあります。大脳を上から見ると前頭葉、頭頂葉、後頭葉と並んでおり、左右に側頭葉が位置しています。内側に大脳辺縁系があります。大雑把に言えば、側頭葉は人間の知能に重要な役割を担う言語機能、そして記憶や本能・情動を司ります。奥の方の大脳辺縁系に海馬という、形状がタツノオトシゴに似ている部位があって、ここが記憶の中枢です。前頭葉は体全体の感覚から得られる形や重さ、手触りといった印象を認識したり、それらの情報を統合したりする中心です。自分の位置や方向の把握といった空間認識や複雑な動作、計算なども司ります。後頭葉には視覚野の中枢があり、視覚情報を処理しています。色や形、明るさや奥行き、動きなどを把握するわけですが、これらの情報を頭頂葉や側頭葉、さらには前頭葉とやり取りすることで、目に映った状況を「あ、車が近づいてきているのだな」と把握し、「避けなければ」などと判断します。脳というのはこのように、各部位が相互に連携を取り合って機能しています。前述の大脳辺縁系は本能や感情を司ります。大脳が発達しているのが人の脳の特徴ですが、なかでも前頭葉の大きさは大脳全体の約30%を占めます。だからというわけではありませんが、前頭葉の役割は多岐にわたります。運動する時や言葉を操るとき、泣いたり笑ったりするときに働くのが前頭葉です。
前頭葉はさらに「前頭連合野」「ブローカ野」「運動前野」「補足運動野」「前頭眼野」「一次運動野」に分けることができるのですが、それぞれに高度な機能を担っています。中でも「前頭連合野」は思考や判断といった情報の処理や、集中力や意欲、情動のコントロール、創造性や計画性、社会性といった“人間らしさの源泉”ともいえる役割を担います。前頭葉の機能がすべて解明されているわけではありませんが、前頭葉とはいわば、人間の“知性”そのものを司ると言い換えてもいいかもしれません。
人の感情は大脳辺縁系という、前頭葉よりずっと奥、脳のもっとも内側にある深い領域で生起されます。その感情に対して、これまでの経験や知識を動員して、行動にブレーキをかける役目を果たすのが前頭葉です。ところが前頭葉の機能が低下してしまうと、経験や知識がむしろ「かくあるべき」「なぜこうならないんだ」と怒りや悲しみを強化してしまう。
記憶から感情まで、当たり前ですが、毎日を過ごす、健全に過ごすためのおおもとが、ここに集積されているわけです。
では、この前頭葉、いつまでも生き生きと、活動してくれるものなのでしょうか?
そもそも、人間の脳は加齢とともに小さくなります。これは、前頭葉も例外ではありません。それどころか、真っ先に委縮を始めるのが前頭葉なのです。
脳の老化は前頭葉から始まります。そして、前頭葉は感情のコントロールを司ります。前頭葉の老化は、感情の老化でもあるのです。
当たり前ですが、加齢とともに退化していくのです。それが、もの忘れ、思い出せない、ということにつながるのでしょうか。
現在、知能は流動性知能(fluid intelligence)と結晶性知能(crystalized intelligence)に分けられるとされます。処理スピードや直感力、何らかの法則を発見する能力など、新しい情報を獲得して処理、操作する知能を流動性知能と言い、これは20代でピークを迎えた後は低下してゆきます。ところが言語能力、理解力、洞察力といった、個人が長年にわたって経験し、教育や学習などで得た知能を結晶性知能というのですが、こちらは60代70代になってもなかなか失われないどころか上がっていくという報告もあるのです。判断力や推理力、発想力、記憶力、計算能力などの能力は、この2つの知能の双方が必要とされ、こういった能力も55~60歳まで高く維持され、明確に低下するのは80歳以降とする研究もあります。
(思い出せないなどの)このタイプの物忘れは、認知症であったり、その他何か不可逆的なトラブルが脳に起きているというよりは、「想起障害」と言って、それほど心配する必要のない症状であることが大半です。しばらくして思い出せたり、ヒントから思い出せたりすれば正常レベルです。
なのだそうです。人間の脳も容量があり、年齢を経るほどにそのメモリーを使っているので、削除しなければ、そこへの記憶や情報の引き出しにも、すこし制限が加わるのですね。
では、前頭葉の衰えの兆しは何か?以下の5つを挙げています。思い当たるところがあれば、要注意です。
前頭葉の機能不全①「保続」 – 世間の新しいルールやしきたりについていけなる
前頭葉の機能不全②「変化に気付けない」 – 変化のない状態を好むようになる
前頭葉の機能不全③「ワンパターン」 – 自分の行動がワンパターンになっている
前頭葉の機能不全④「アウトプットできない」
前頭葉の機能不全⑤「無関心」 – 「新しい話題やニュースに関心が向けられなくなった」「最近、仕事に関する情報のキャッチアップができていない
前頭葉の機能不全⑥「孤独」
前頭葉の機能不全⑦「やる気が出ない」 – やる気を失い、挑戦や変化を遠ざけて現状維持を求める
この保守的な思考、行動を自分自身で感じ始めれば、これは明らかに、おかしい、年取ったと感じるはずです。こわいのは、意識しないでこのような行動をとっている時ですね。では、こうした事象の発現が、少しでも遅くなる(ないのが理想ですが…)ために、どうしたらよいのか?筆者は、前頭葉を鍛える5つのことを、提案してくれています。
前頭葉を鍛える5か条
-
「二分割思考」をやめる
- 他人の意見に流されず、自ら調べて自分の頭で考えて、答えを1つに決めつけない。世の中や「正解」というのは変わっていくものですし、いったん賢くなったらずっと賢いわけではありません。思考にグレーゾーンを設けることを心掛けたいものです。
-
実験する
- 「二分割思考」から解放されたのですから、「答」を得て満足せず、ルーティンを避けてさまざまな「初体験」を求めて実験しましょう。対象は何でもいいのです。必要なのはフットワークの軽さです。
-
運動する
- やはり、身体活動抜きに脳の血流だけを活発にするには限界があります。昆虫採りでもラーメン屋めぐりでもよいですから、身体を動かすことは前頭葉の活性化のためにも心掛けた方がよいでしょう。
-
人とつながる
- 孤独は脳の老化を促進しますし、人を思いやる感情は前頭葉の重要な役割です。人とのつながりはソーシャルスキルも育みますし、何より、他人ほど予想のつかない存在はありません。前頭葉がもっとも働く瞬間を大事にしましょう。
-
-
インプットももちろん大事ですが、インプットしたものをただ「再生」するのではなく、「加工」してアウトプットすることが大事です。「人とつながる」ためにも、前頭葉をフルに使ってアウトプットすることを心掛けてみてください。
当たり前ですが、とにかく面倒くさがらずに、頭を使うことなんですね。そして、”ワオ”という、外からの刺激から、内なる脳を刺激し、駆動させる。
前頭葉を鍛えるためには「刺激」が必要だという話をしてきましたが、これはもちろん、刺激が脳を活性化する、脳の血流を増大させるからです。脳の血流が増えることで脳が賦活化、意欲がまし、そのことがさらに刺激を求める・・・・という好循環を生みだせばしめたものです。
前頭葉は「新たな発見」を求めています。これから高齢者が増えていく中で、どうやって老後を過ごすのかということをよく聞かれたりしますが、そういう時は「生きることを実験だと思えばいい」と申し上げることにしていて、生きることが実験だと思えれば、失敗はさほど怖れる必要がありません。うまく行かなければ、また別な実験をすればいいという考え方ができるでしょう。
実は「アウトプット」こそが前頭葉の活性化には大事です。地域のグループに参加してもいいでしょう。夫婦仲をよくする努力をしてもいい。考えたことをSNSに投稿して仲間を募るのもいいでしょう。年を取ったら、「聞く力」より「発信する力」をどう伸ばすかが重要だとわたしは思っています。
「自分を楽しませる」「人を楽しませる」ことが結局、前頭葉を活性化し、ひいては健康寿命を招くということです。
50代で意識してほしいのは運動です。
要注意なのは、「やる気が出ない」「不調が続く」といった症状です。前頭葉の老化が原因かもしれませんし、初老期のうつや運動不足、男性でもホルモンバランスの崩れによる更年期障害の可能性もあります。
セロトニンや男性ホルモンを増やすには、肉やコレステロールを摂取するとともに、運動をし、日光を浴びることです。認知症を予防し、進行を遅らせるためには、意識的に運動し、頭を使うことです。
高齢になるほど心と体の状態がリンクしやすいので、見た目も若さを保てるならば保った方が良いです。かつらやボトックス注射などで若返りをはかるのは悪いことではありません。こうしたことも前頭葉を若く保つことにつながります。
自分が楽しい、やる気になることは、何でも試せ、ってことです。
そして、私が優れたリーダーとなるためには、「心技体」を高いレベルで身に着けておく必要があると考えているわけですが、筆者も同じような見解を示されています。(リーダーを、「優秀」とされていますが。私は「優秀さ」とかは、まあいいかなと思っています。
「優秀」であるとは、インプットに相当するIQと、前頭葉を使ったユニークでかつ説得力のあるアウトプットに相当するEQが揃って初めていえることなのではないか、とわたしは思うのです。答えがあらかじめ決まっている暗記試験やペーパーテストでいい点を取れるだけではなく、自分や社会が直面している「答のない」問題の解決の糸口を探り、自分なりに加工・編集して他者に伝え、試行錯誤しながら解決へと導いていける人と言えばいいでしょうか。わたしはそうした優秀さを持つ人が本当の意味で「頭のいい人」だと思いますし、言葉を変えれば、「前頭葉を有効に使える人」なのだと思います。
健全な精神や身体を維持するためには、脳の働きを少しでも理解した上で、日々過ごしていけると、その積み重ねは大きいかもしれません。