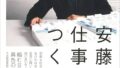前回は、レイ・カーツワイルの『シンギュラリティはより近く 人類がAIと融合するとき』をご紹介し、これからの世の中がどうなっていく可能性があるのか、考え方の1つをご紹介しました。もう1作、今回も将来の世界、人間がどうなっていくのかを考えるきっかけになる1冊をご紹介したいと思います。
川口 伸明 著作による、『2080年への未来地図』 です。
著者はアスタミューゼ株式会社のチーフ・サイエンティストで、本著は未来がどのような世界になっていくのか、膨大な論文やリサーチの探索から、テーマ毎にまとめられた本です。
カーツワイルと同様に、特にAIがかかわる未来について、印象に残った部分を共有します。本当に印象に残った部分で、ではそれがどうなるのか、どうしたらいいのか、については、特にこれからリーダーシップを育んでいく上では、我々が自問自答しなくてはいけない問いなのかと思います。
2030年代後半までに、ASI(人口超知能)が登場する可能性がある。それがシンギュラリティの出発点となるだろう。AIの研究開発現場への適応では、現状では、人が主導する研究開発をAIがサポートするAI-supported scienceが主流だが、シンギュラリティ以降、AIが自律的に研究開発をおこない、発明・発見をするようなAI-directed scienceが始まる可能性がある。AIは医療や産業、環境、エネルギー、経済安全保障など広範な社会課題の解決に必須のものとなりつつあり、AI研究への過度の危惧や抑制は、かえって未来の選択肢を狭める方向にミスリードする可能性が大きい。最先端のAIは人間では認識できないような認知や計算が可能であり、人類未踏の新しい科学技術の発見や発明に力を発揮することが期待される。人類にとっての新しい顕微鏡や望遠鏡のような世界のセンサーとしての役割を担う可能性がある。AIが主導的・自律的に研究開発や発明・発見を行う「AI-directed science」と、これまでどおりの人間主導でAIを活用する「Human-directed AI-supported science」の2つの方向性があると考えられます。今後、各研究機関などで個別に学習したAIが論文を書く場合、論文著書として、AIの仮想的な人格を持った個人としての名前を書く時代が来るのではないかと思います。同様に、AIが書画を描く場合も、AIのアーティストとしての個人名のサインを入れるのが当たり前になるでしょう。
AIが必要か?という議論ではありません。
AIが人間の認知能力を超える中で、どのように「共創」していくか。それこそが考えなくてはいけないことです。
私が生業にしているヘルスケアの世界も、こんな世界になる可能性がある。
2030年代にはメタバース医療が遠隔診断を中心に本格化、2060年代には医・食・農がシームレスにつながった未病医療が体系化されるだろう。2080年代までに、デジタルヘルス、プレシジョンメディスン、マイクロバイオーム、ブレイン&マインドの漸進的データをいつでもどこでも自動的にスキャンできるトータルボディスキャンが可能になるだろう。医療にメタバースを導入する動きは始まっており、いつでもどこでも標準的なレベルの医療が受けられるという医療の均霑化、医療ひっ迫の回避、医療アクセスの民主化などに貢献することが期待されている。プレシジョンメディスンの進展で、血液だけで認知症やMCI(軽度認知障害)を検出できるバイオマーカーが開発されている。また、空間転写プロファイリング(空間トランスクリプトミクス)により、がん組織などの空間全体での遺伝子発現の分布をみることで、病態の進行などより詳細な診断が可能になってきた。AIの医療への導入により、画像診断やバイオインフォマティクスだけでなく、創薬、完全自動ロボット、医師の患者とのコミュニケーションのサポートなど応用範囲が広がっている。量子AIなど量子コンピュータの活用にも期待が高まっている。脳腸相関などマイクロバイオーム(腸内細菌叢)による時計遺伝子や長寿遺伝子などの生体制御の可能性がある。認知症や睡眠障害などメンタルヘルスのほか、高血圧など心肺循環器系疾患、免疫代謝系疾患など、さまざまな疾患の罹患リスク推定や症状の緩和、予防などに応用できる例が報告されているウェルビーイングの流れとして、医食同源的な発想で、食と健康の関係性、生活習慣や環境との共生、マインドフルネスのようなメンタルのマネジメントが注目されている。
ただし、当然、以下の課題があると記述しています。道徳性、公共性、プライバシーと法整備については、今後の大きな争点になっていくでしょう。
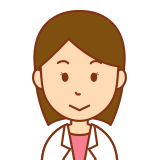
医療におけるメタバースの4つの課題
- ガバナンスと法整備
- 個人健康記録(PHR)活用の促進(デジタルツイン情報を含む)
- 個人の権利保障
- 公平性とインクルージョン(包括性)の確保
そして、我々人間の生命や思考に対しても、大きな転換を迫られるかもしれません。
デジタルな人工意識やマインドアップロードが可能となったとしても、人間が死ぬことに変わりなく、アップロードした意識は自分の意思を受け継いでいるが、自分本体ではなく、自分のアバターへのバトンタッチである。それを許容するためには、死生観や実存価値の転換が前提になるだろう。しかし、それを受けれ入れたならば、新しい生の形となり、自分の寿命にこだわらず、自分の仕事を継続したり、より進化させたりすることも可能となる。マインドアップロードやスキルトランスファーなどにおいて、脳と脳、脳とクラウド間での情報伝送に必須となる情報のエンコード-デコード(暗号化と解読)のうち、デコードの実証が進んでいる。特に、脳内で思考中の言葉や見ている画像を外から非侵襲的に解読、再現することが可能になってきた。デジタルな超長寿化により、人間はより深遠なテーマ、より好奇心を追求するようなテーマに関心を持つようになるかもしれない。心理的な時間だけでなく、物理的な時間もまた、一般相対性理論に従い、1人1人の物理的履歴によって異なってくる。その時間をどう活かすかが問われる。戦争を超えて、人類の未来のための意味と価値の創出が重要な時代に入った。
肉体を超えた生の拡張。認知世界の拡張もです。
生成AIとメタバースの連携で、言葉で表現できるものは形にできる。それに空間知能化したASIが加わることで、人間が知覚できないものも形にできる。さらに、ブレインテックを取り入れることで、考えたこと、夢に見たことさえも形にできる時代が来るかもしれない。頭の中で考えていることが言語化される非侵襲的な「言語脳-コンピュータインタフェース」の実現可能性が示されたことで、将来的には、障害を完全に克服し、自らの脳の理解を深めることができるかもしれません。しかし、潜在的には個人のプライバシーや自由な思考の脅威となる可能性もあると、研究者らは警鐘を鳴らしています。今後は、ウェアラブル化も可能なfNIRS(近赤外分光法)などの、ほかの脳画像システムへの応用を検討するということです。AIによって、脳の中で起きていることのごく一部ではありますが、外から比較的手軽に解析することができるようになれば、医療や心理カウンセリングのほか、教育や犯罪捜査など、さまざまな応用の可能性が広がります。また、意外と人の脳内メカニズムはシンプルなモデルで説明できるかもしれないとも感じます。
その帰結として、新たな死生観も生まれてくる可能性もあります。
生と死を明暗で分けでしまうのが今の常識ですが、さほど遠くない未来に、おそらく、人類は生の新しい形を求める道へ進むのではないかと思います。100年の命ではなく、数百年、数千年生きるかもしれないバーチャルな命に、自分の命をバトンタッチすると考えたら、人間の世界観も、生き方のパラダイムも大きく変わるのではないでしょうか。アバターの寿命に合わせて、より長い時間軸でこの世界を認識し、未来を考えられるようになるのではないかと思います。現在、自分の死後を考えてみても、どうしようもないことです。しかし、マインドアップロードでは、AIとメタバースの連携で、自分の死後の人生、つまり、自分の遺志を受け継いだAIアバターの人生をデザインすることはある程度可能になると思います。生身の自分はせいぜい百年前後で死んで消滅してしまいますが、自分の医師を受けつぐASI(人口超知能)アバターやロボットなどで身体性を与えられたAIエージェントに自分の未来の仕事を託すことはできます。そして、「彼・彼女」は、時間や環境の変化とともに成長し、さらに考えやふるまいが進化していき、自分では達成できなかったところまで到達してくれる可能性があります。だとしたら、自分がいない未来にも、「自分ごと」として希望や関係性を持ち続けられる気がします。寿命を縦に伸ばしていくのは難しいですが、メタバースやパラレルワールドで横に拡張して同時多発的にいろいろな人生を送ることや、マインドアップロードでアバターAI(自分のデジタルクローン)に仕事や知識を継承し、自分は永い休眠に入るという生き方も射程に入ってきたのが現実です。マーラーの謳う「新たな生への飛翔」に近い感覚だと思います。超長寿社会の先には、もはや生物学的年齢ではなく、挑戦脳年齢や好奇心年齢といったものが意味を持ち、知の民主化はもとより身体性の民主化、生き方の民主化といったことが一気に進む時代が来るかもしれません。
生き方、テクノロジーを通じた人とのかかわり方、働き方、新たな政治・経済のシステム。。。すべての人がリーダーシップを持って、自律的に生きていくこと、生にかかわることが求められる来るのかもしれません。