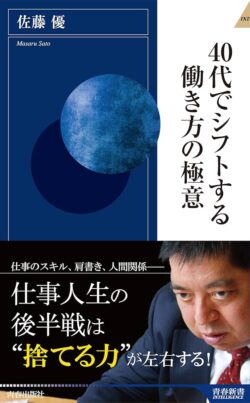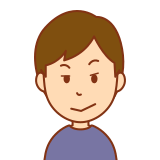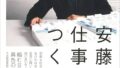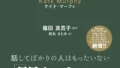リーダーシップを磨き、優れたリーダーとなるためには、『心技体』を磨き続けなくてはいけない。
『技』は、常にアップデートを続けなくてはいけないですが、生成AIがこれだけの精度で利用できるようになった最近では、必ずしも自らすべての技を身に着ける必要はなく、それを使いこなすだけの技量が必要になってきました。
さらに重要になってくるのが、『心』の部分だと思います。今回は、その参考となる、佐藤優さん著作の、『40代でシフトする働き方の極意』 をご紹介します。
佐藤優さんは、元外務省の分析官で、その後は、政治、社会についての鋭い論考を多数発表されているのは、ご存じの通りかと思います。この『40代でシフトする働き方の極意』 は、人生の半ばをさしかかる年代で、企業組織内の立ち位置やリーダーシップ、また残りの人生の生き方戦略について、佐藤さんの自論が展開されています。
『技』を磨くために、『心』の持ち方で、参考になったのは、以下のような姿勢です。
人生の師は色々なところにいる。一緒にいていやされたり、楽しかったりする存在も、広い意味でメンターだと考える。色々相談でき、そばにいるだけで安心する。そんな存在も必要です。よきメンターにめぐり合い、よい関係を築くのに必要なのは、「素直さ」だと思います。相手を尊敬し、相手から学びたいという姿勢、ひたむきな気持ちがあるかどうか。それは敏感に相手に伝わります。教えたことを素直に学び、自分に取り込もうと頑張る姿勢、そして成長していく姿に、相手もその気になって真剣に向き合ってくれます。また自分をさらけ出せる潔さも必要でしょう。知らないことを知らないと認められるかどうか。よく人から何か教わると、いかにも知っていたかのように振舞う人がいます。反対にかわいがられるのは、自分が知っていることでも知らなかったように反応できる人です。「そうですか、勉強になります」など教えてくれた人を持ち上げるのは、ずるいのではなく、優しさや礼儀の1つです。
佐藤さんのように膨大な知識量を持ち、それを莫大な努力で培ってきた人が、『素直さ』が大切だと説く。
私も、この『素直さ』はきわめて大切な姿勢だと考えていて、歳を重ねるほどに「素直に」色々な人から教えてもらうことで、常に最新の知識や知恵にアップデートできると考えています。人を採用する際にも、私は『素直さ』を1つの基準にしているくらい、大切な『心』の持ち方だと思っています。
また、人の感情については、自分が実際に対面で経験できるには、限界があります。そこで、ビジネスパーソンにこそ、「疑似体験」が役に立つことをおっしゃっています。
ビジネスパーソンにこそ小説が必要。優れた小説には作者の感性や感情が様々な形でちりばめられています。深い内面の思索の中で、私たちの日常の常識を超えた解釈や感性が明らかにされていることもある。たとえば犯罪小説には、表面的な犯罪心理学の理論よりずっと深い考察が繰り広げられていることもあります。また、社会的に落伍したアウトローや裏社会などを描いた小説を読むと、社会通念や常識を相対的に捉えることが出来るようになる。単純に善悪や正邪で二分できない世界があることを知るだけでも、思考の幅は広がるでしょう。自分とは違う世界の住人たちのストーリーを読むことで、私たちはあたかも自分がその体験をしたような感覚に陥る。このような代理経験をつむことによって、実体験に勝るとも劣らない知識や知を得ることが出来ます。
本当にその通りです。自分と違う考え方にこそ、気付きやそもそも「こんな考え方するんだ」という自分との違いそのものの引き出しを増やすことが出来ます。
さらに、自分の感情を適切にコントロールすることについても、経験論から指摘しています。
自分の感情をコントロールできない人は、全うな交渉もまして大人のけんかも出来ません。外務省でもやたらと怒鳴り散らすような人は、「あの人は情緒不安定だから」という評価になりました。そう言われたらすでに人間的信用力ゼロ。出世の道は閉ざされます。けんかする相手を間違えている人もいます。正義感に駆られて、会社や上司に反抗したりけんかを売ったりする。組織に属している限り、絶対に上司とけんかをしてはいけません。組織とけんかしてもまず勝ち目はありません。
相手とぶつかる際に大切なのは、「攻め」ではなく、実は「守り」。攻めに強いけど守りに弱い、という人がいます。会社におけるリアルな話で言うなら、領収書の出し方1つにもそれが表れます。守りによわい、というのは言い方を換えると、「脇が甘い」ということ。
EQリーダーシップの最初は、自分を知ること。そして、自分の感情をコントロールすること。それが適切な対人関係を築いていく上での礎であることが、個々でも確認することが出来ます。
その上で、リーダーとしての組織の「感情のマネジメント」の部分で、プラクティカルな興味深い指摘もありました。
リーダーとして部下をまとめていく上で重要なポイントは、「嫉妬のマネジメント」です。今は、褒めるのも呼び出して、こっそりほめたほうがいい。特定の人をメンバーの前で褒めた途端、その他のメンバーが嫉妬してしまうからです。私の推測ですが、昔より自己愛の強い人が増えたということかもしれません。自己愛性パーソナリティ障害の人は、自分が常に主役でなければ気がすまない。そこまで病的でなくても、傾向として自己愛が強い人が増えているように感じます。自己愛が強い人は、無意識では自分に対する自信が欠如しています。それを補うべく他者の賞賛や承認が必要になる。いつも注目を浴びていたいし、「すごいね」と賞賛を浴びていたい。その強い志向が、他者が注目され、ほめられたときにはたちまち嫉妬という強い感情に転換されるのです。
部下のマネジメントは、今の会社組織の中で、本当に難しくなってきています。それを教育制度や家庭の在り方に原因を押し付けるのは簡単ですが、でも毎日の日常でいかにチームメンバーの能力を最大限に発揮してもらうためには、こうした感情のマネジメントも必要になる。これは『心』に適切に対処する『技』なのかもしれません。