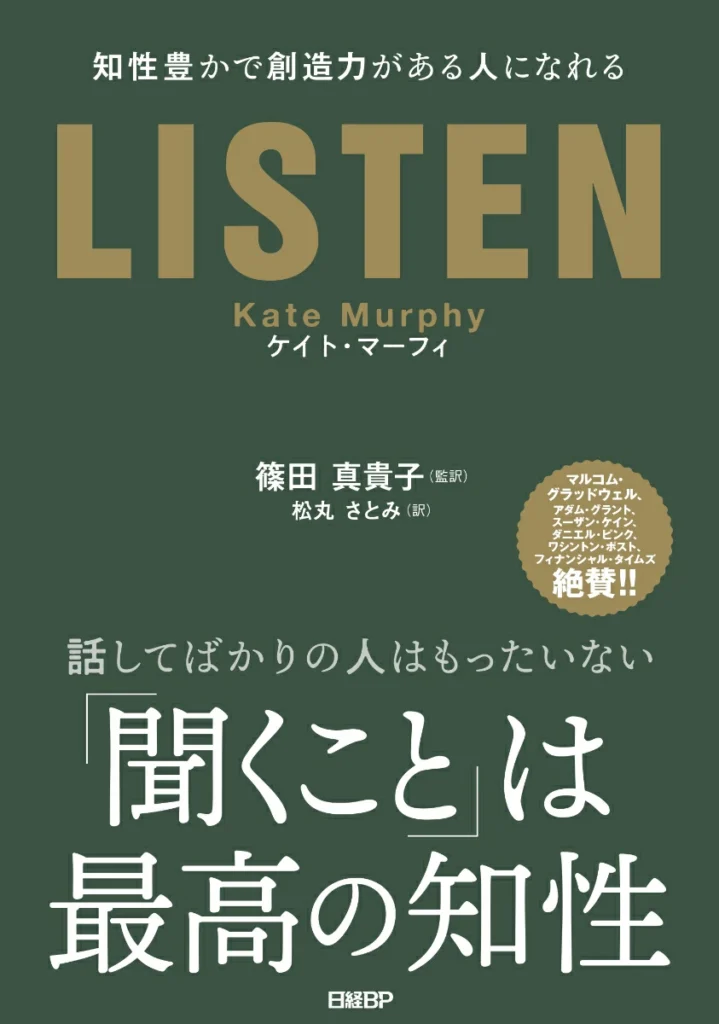リーダーシップを磨き、優れたリーダーとなるためには、『心技体』を磨き続けなくてはいけません。
『聞く』-それは、『心』や『技』を磨くにあたって、とても大切なスキルや心持ちですが、自分では「聞いている」と思っても、そうでない場面も多くあるのではないでしょうか。私は、できなかった。いや、今もできるようになったかは、自信がありません。妻と会話をしていても、「次にどうやって自分の言葉を返そうか、そればっかり考えてるでしょ?」とよく詰められたものです。
ビジネスのスキルを学ぶ機会のある方たちは、「アクティブリスニング」といったクラスを見かける方もいると思います。これも立派なスキル=『技』ですし、そのためには心構え=『心』を知っておく必要があるわけですね。
今回は、聴くこととは何か、参考になる書籍をご紹介します。ケイト・マーフィー 著作の『LISTEN』 です。
ケイト・マーフィーは著名ジャーナリストで、数多くの著名人とのインタビュー経験を実施し、その人の考え方を世に発信してきている人ですが、より突っ込んだ話、その人の真の声を引き出すことを目指した中で得た「本当に人の話を聞くとはどういうことか?」という彼女なりの考え方をまとめた書籍です。
まず、「聞く=Hearing」と「聴く=Listen」は違う、としています。
「ヒアリング(聞こえること)」は「リスニング(聴くこと)」とは同じではなく、むしろその前段階にあるということです。「聞こえる」は受動的です。「聴く」は能動的です。もっとも優れた聴き手は、聴くことに意識を集中させ、聴くために他の感覚も動員します。脳みそをフル稼働させて入ってくる情報すべてを処理し、そこから意味を引き出します。ここでつかんだ「意味」が、創造性、共感、洞察、知識へとつながる扉を開きます。聴くことのゴールは理解です。聴くことには努力が必要です。相手の言葉に真摯に関心を示し、もっと聞かせてほしいと言うと、彼らは驚いた顔をします。そして私が話を急かしたり、言葉を遮ったり、スマホに目をやったりしないと確信すると、目に見えてリラックスして、じっくり思いを巡らせ、考えたことを省略せずに話すようになるのです。私たちは聴くことでしか、人として関わり、理解し、つながりあい、共感し、成長できません。聴くことは、プライベートであれ、仕事であれ、政治的なものであれ、どのような状況においても、人間関係がうまく行くための土台をなすものです。
しかし、誰でも「自分は人の話にしっかりと耳を傾けている」と自分自身は考えているかもしれません。しかし、こんなことはないでしょうか。
悲しいことですが、私たちはきちんと話を聞いてもらえた経験よりも、無視されたとか誤解されたと感じた経験の方が多いのです。ここで、だめな聞き手の行動としてよく指摘されるものを、列挙してみましょう。
イギリスのエセックス大学で心理学者らが行った研究によると、テーブル上に携帯電話があるだけで、たとえ音が鳴っていなくても、そのテーブルに座った人たちはお互いに親近感を抱くことはなく、大切な話や深い話をしたいとは思わないことがわかりました。もしそんな話をしても、おそらく邪魔が入ると思っているからです。聞く価値おない話を人がするような状況を作り出し、その結果、人はますます聞くのを止め、携帯電話を見るようになるー携帯電話が作り出す摩訶不思議なループです。音が鳴っていても、私は気を散らさず無視できる。そう思うかもしれませんが、それは無理であることが研究によって繰り返し示されています。マルチタスクができるなど、幻想なのです。何か情報がひとつ入ってくるたびに、注意力は低下します。この意味するところは、人の話に本気で耳を傾けるには、適切な環境を整えなければならないということです。受け入れるための物理的空間も、心の状態も整える必要があります。静かで、邪魔が入らない状態を確保しましょう。
まず、集中して、『聴く』という環境を整え、相手を安心させること。また、こんなこともしていたりしませんか?
気が散る最大の原因は、「次にどんな気の利いたことを言おうかな」とか、もし言い争いの場なら「次にどんな破壊力のあることを言ってやろうか」といった、次に何を話そうかと考えることです。頭の良い人は話を聞くのが下手なことの方が多いです。というのは、他にもっといろいろな考え事を思いついてしまう上、相手が話そうとしている内容を自分はすでに知っていると決めつけがちだからです。IQが高い人はまた、神経質かつ自意識過剰になる傾向もあります。つまり、不安や心配事で頭がいっぱいになってしまいやすいのです。会話が耳に入ってこない原因は、「話すことと思考することの違い」にあります。これは、人の思考は話すことよりもずっと速いという事実を指しています。ニコルスによると、優れた聞き手は、余っている処理能力を頭の中での寄り道に使わず、相手の話を理論的にも直観的にも理解するために全力をあげているといいます。また、しっかりと聞くことは、話し手の言わんとしている内容は妥当か、その話を聞かせてくれる動機は何かを、自問し続けることだともニコルスは述べています。心をしっかりと相手の話に集中させて聞き続けるにあたり、いちばんの障壁はおそらく、自分が話す番になったら何を言おうかという心配が頭から離れないことでしょう。結論から言うと、次に何を言おうかという心配は、自分のためにならないということです。自分の考えから心を解放して、相手の話に耳を傾けた方が、もっと良い反応ができるようになり、相手とのつながりは強くなり、気持ちは落ち着きます。また、よりたくさんの情報が得られるようになるため、会話がもっと面白くなります。それは、言葉を聞いているだけでなく、脳の余力を使って、話し手のボディランゲージや声の抑揚に注意を払い、話の文脈や動機も考えるようになるからです。
私は妻にもよく指摘されていたと書きましたが、全くその通りでした。それはなんでかな、と考えたときに、私は仕事柄、今のビジネスを上層部に説明する機会が多かったのですが、その時は「何か質問されたら適切な回答をしよう」と常に戦闘モードというか、防御モードというか、そんな状態なのです。海外とのやり取りも多いので、余計話が終わるまで全部待っていたら、次から次へと話が展開し、むしろ自分の「バリュー」を出せないようになってしまう。顧客と対する時も、やはり「しっかりとした対応が必要だし、ちょっと気を利かせた返しもしたいな」なんていう、色気も持っていたりする。
だから、普段の会話の中でも、常に「この先に自分がどんな話を載せていくかな」ということばかりを考えるようになったのかもしれません。
「相手の話を、虚心坦懐に、聴く」ということをできるようになってきたのは、本当にここ最近のことかもしれません。さらには、ただ聴くだけで、それに対して何も返さず、考えを深めていってもらうような相槌しか打たないことも多くなりました。
そのようになるために、何かスキルが必要なのでしょうか。
聞き上手は、「消極的能力」を備えています。相容れない考えや白黒はっきりしないグレーゾーンに耐えられるのです。優れた聞き手は、人の話にはたいてい、一見しただけではわからない何かがあると理解しており、理路整然とした根拠や即座の答えにそこまでこだわりません。これは「狭量」の対極にあるものといえるでしょう。心理学の分野では、消極的能力は「認知的複雑性」として知られています。研究によると認知的複雑性は、セルフ・コンパッション(自分を慈しむ気持ち)と正の相関であり、独断性と負の相関があります。認知的複雑性を持っている人は、不安を感じることなく人の話を聞き、あらゆる意見に耳を傾けることができます。認知的複雑性が高い人ほど、情報を蓄え、思い出し、整理し、生み出すのが得意で、そのために何かを結び付けたり、新しいアイデアを思いついたりする器用さがあります。また認知的複雑性のおかげで、より的確な判断や妥当な決断を下せます認知的複雑性とは、さまざまな経験にオープンであり、反対の意見にも対処できるということです。多くの人の話を聞いた経験がないと、会話に出てくる微細なシグナルにうまく気付くことはできません。直感や第六感と呼ばれるものは、実は気付く力でしかない、と言われます。多くの人の話を聞けば聞くほど、人間が持つ多様な側面に気付くようになり、直観もさえるようになります。これはいかに幅広い意見、態度、信念、感情に触れるかによって決まる、実践的なスキルです。
要は、ひたすらに『聴く』経験を積む、これが大切なのだと。興味深いのは、そのような姿勢をチームとして持っていると、生産性の高い成果を期待できると。
もっとも生産性のあるチームは、メンバーの発言量がだいたい同じくらいだということでした。これは、「会話での平等な話者交代」として知られています。能力の高いチームはまた、「社会的感受性の平均値」が高いこともわかりました。つまり、声のトーンや顔の表情など非言語的な手掛かりをもとに、お互いの感情を直観的に読み取る能力に長けていたのです。言い換えると、グーグルの調査で明らかになったのは、成功するチームではメンバーの話をお互いに「聴き合って」いたということです。メンバーは交代で発言し、お互いの話を最後まで聞き、言葉にされていない考えや感情を理解するために、非言語の手がかりに注意を払っていました。そのため、チームの人たちは思いやりがあり、その状況にあった反応をするようになりました。さらに「心理的安全性」と呼ばれる、言葉を遮られたり意見を一蹴されたりする心配をせずに、情報やアイデアを交換しやすい雰囲気をつくっていたのです。
イノベーションや質の高いアウトプットを出すための土台として、「心理的安全性」が担保できる環境にすることを私は重視していますが、『聴くこと』を通じて、自分を理解してもらえるという「心理的安全」な環境を作れるのですね。当たり前と言っていいかもしれません。
誰もがこのような境遇を求めているわけではないでしょうし、自信の置かれた状況、立場によるとは思いますが、優れたリーダーとなるために知っておいていい『技』であり、『心』ではないでしょうか。
「自分を売り込む」風潮が強い中で、「口先だけで人間関係を手に入れることはできない」という事実がなんとなく見失われているのではないでしょうか。言葉をまくしたてるおしゃべりは沈黙を埋めますが、その分、相手と自分との間に、言葉でできた壁をつくってしまいます。その点、沈黙は、相手をこちら側に受け容れます。沈黙は寛容なだけではありません。はっきりとした利点もあります。沈黙をいとわない人は、より多くの情報を引き出します。居心地の悪さからしゃべりすぎるなどということもありません。
あなたができる最善策は、相手の話にただ耳を傾けることです。その人が直面しているのが何かを理解しようとし、その感覚を感じ取ってください。
目の前の相手に、寄り添う姿勢、ですね。