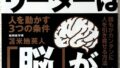リーダーシップとは何か?
リーダーとは、何をなすべきか?
リーダーシップについては、様々な研究が行われていますし、数多くの論文や書籍も発刊されています。大変なリサーチに基づいた学術的な研究理論から、個人の成功体験に基づいたリーダーシップ論まで、様々です。
またリーダーたること、リーダーシップを発揮するべき環境も、必ずしも企業組織内、ビジネスに関わる場面のみならず、関わるコミュニティや、家庭内まで、様々な場面があるかと思います。
私自身がリーダーシップについて、色々な人に学び、書籍に触れ、考え続けてきたのは、あくまで私自身が「どうしたら優れたリーダーになることができるか」という、個人的内発的動機が発端で、各人各様で、色々なリーダーシップの定義があってよくて、自分で納得がいって実践できるものを、実際に試して、身に着けていけば良いのかなと思います。
ですので、リーダーの定義も千差万別、リーダーシップの定義も千差万別。言えるのは、その場その場で求められるリーダー像、リーダーシップスタイルは異なってくると思うので、多くの引き出しを持っていることが大切なのかな、と思います。
私が自分なりに行き着いたのは、『心技体の高みを極める』 ということになるわけです。
まあ、こんな御託は置いておきまして、リーダーシップについて、大きく影響を受けた書籍を紹介したいと思います。
ジェームズ・C・コリンズによる、『ビジョナリー カンパニー② 飛躍の法則』です。
超直球、ど真ん中くらいかと思います。この本から学んだことを紹介しようと思うと、大作になってしまいますので、私の考え方に影響を与えた、エッセンスのみを紹介します。
この研究は、15年間にわたって市場を平均して3倍以上の成果を出した、『GOOD』から『GREAT』に飛躍した企業を抽出して、その要因をリーダーシップや企業文化、戦略などを分析しています。
その中で、もっとも私に刺さったのは、
『偉大な飛躍を遂げた企業はすべて、『第五水準』の指導者が指揮をとっていた』『第五水準のリーダーは、職業人としての意志の強さと、個人としての謙虚さという、矛盾した正確を持ち合わせている』
という点。
「第五水準の指導者は、自尊心の対象を自分自身にではなく、偉大な企業を作るという、大きな目標に向けている。我や欲がないわけではない。それどころか信じられないほどの大きな野心を持っているのだが、その野心は、何よりも組織に向けられていて、自分自身には向けられていない。」
まさしく、経営スキルだけでなく、人間性、『心』の部分が大きな要素であると説いています。
ちなみに、第五水準に到達するまでの過程は、以下のように定義しています。
第一水準:有能な個人 「才能・知識・スキル・勤勉さによって生産的な仕事をすすめる」第二水準:組織に寄与する個人 「組織目標達成のために自分の能力を発揮し、組織の中で他の人たちとうまく協力する」第三水準:有能な管理者 「人と資源を組織化し、決められた目標を効率的に、効果的に達成する」第四水準:有能な経営者 「明確で説得力のあるビジョンへの支持と、ビジョンの実現に向けた努力を生み出し、これまでより高い水準の実績を達成するよう、組織に刺激を与える」
では、第五水準のリーダーの二面性とは。
職業人としての意志の強さ
すばらしい実績を生み出し、偉大な企業への飛躍をもたらすどれほど困難であっても、長期にわたって最高の業績を生み出すために、必要なことはすべて行う固い意志を示す偉大さが永続する企業を築くために基準を設定し、基準を満たせなければ、決して満足しない結果が悪かったとき、窓の外ではなく、鏡を見て、責任はすべて自分にあると考える。他人や外部要因や、運の悪さのためだとは考えない
個人としての謙虚さ
驚くほど謙虚で、世間の追従を避けようとし、決して自慢しない野心は自分個人にではなく、企業に向ける。次の世代に一層の成功を収められるように、後継者を選ぶ鏡ではなく、窓を見て、他の人たち、外部要因、幸運が会社の成功をもたらした原因だと考える静かな決意を秘めて行動する。魅力的なカリスマ性によってではなく、主に高い水準によって、組織を活性づかせる
偉大な企業にしたリーダーとしてだけでなく、日常生活でもこのような人材というのは、なかなかにお目にかかれない。当時はスキルを磨くことにやっきになっていた私に、「人間性」の部分=『心』も鍛錬する必要を気付かせてくれた、大きな瞬間でした。『心技体』というフレームワークに行き着いた、大きなきっかけを与えてくれた知見です。
では、そんな第五水準のリーダーが、まず行うことは、
『まずはじめに、適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、その後にどの方向に行くかを決めること』
どういうことか。
「最初に人を選ぶ」
適切な人を、バスに乗せる不適切な人を、バスから降ろす強力な経営陣を作り上げる「適切な人材」の判断基準は、学歴・技能・スキル・専門知識・経験よりも、性格を重視している
「その次に目標を選ぶ」
適切な人材が集まった後、偉大さへの最適な道を、見つけ出す
「正しく報いる」
報酬制度の目的は、不適切な人々から正しい行動を引き出すことにはなく、適切な人をバスに乗せ、その後も乗り続けてもらうことにある
とにかく人なのですね。
飛躍に導いた指導者は、人事の決定に極端なまでの厳格さを求めている
第一の方法:疑問があれば採用せず、人材を探し続ける第二の方法:人を入れ替える必要があることがわかれば、行動する第三の方法:最高の人材は、最高の機会の追求にあて、最大の問題の解決にはあてない
もちろんプロセスには厳格ですが、以下でもあるとしています。
厳格なのであって、冷酷なのではない。業績向上の主な戦略として、レイオフやリストラを行うことはしない
リーダーが、人に対してコミットしているのです。
この研究からは、もちろん他にも企業としてどんな立ち位置を選ぶのか(針鼠の概念)など、戦略策定という『技』に関する学びも多いのですが、今日はこの辺までにしたいと思います。
多くの人やビジネススクールでも取り上げられている研究ですので、機会があれば、ぜひ自身の考え方と照らし合わせながら、ブレストをしてみるといいかと思います。