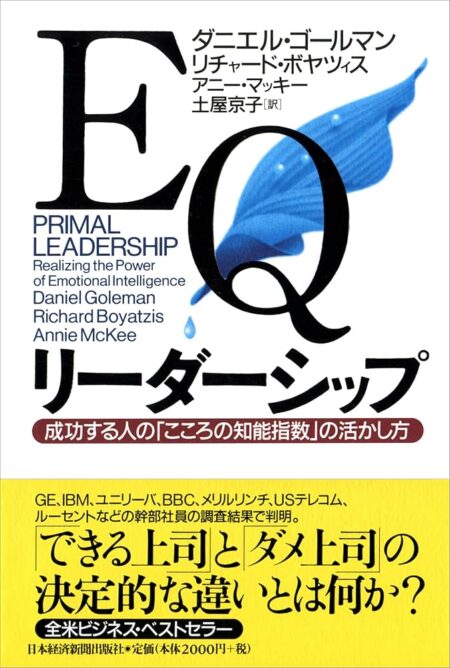前回は、『ビジョナリー カンパニー② 飛躍の法則』という、私にとっては教科書的な書籍の、ほんの一部をご紹介しました。
今回も、私のリーダーシップについての考え方に大きく影響を受けた、もう1冊の教科書をご紹介します。
ダニエル・ゴールマンらによる、『EQリーダーシップ: 成功する人のこころの知能指数の活かし方』です。
『EQリーダーシップ』は、組織を率いるにあたっては、、論理的思考や経営、マネジメントといったハードなスキルを備えているだけでは十分ではなく、感情的知能(EQ)=『ソフトな技』を活用したリーダーシップの重要性について、説かれています。こちらも、生身の人間を動かすことなくして、組織の目的を達成することはない、人へのアプローチを重視したリーダーシップスタイルです。
こちらもすべてを紹介するとこれだけで膨大な知になりますので、今回はその中でも基礎になる考え方をご紹介します。
根本的な考え方は、こちらです。
『優れたリーダーは、人の心を動かす。』
優秀なリーダーシップは、知と情が両方そろったときはじめて可能になる。リーダーは、まず、取り組もうとする課題を理解できる程度の知性を備えていなければならない。もちろん、分析的・概念的思考ができる明晰なリーダーは優秀だ。が、知性や明晰な思考力は、リーダーの前提として要求される素質だ。その上で優れたリーダーになるには、知性以外にも必要なものがあるのだ。リーダーは人々にモチベーションを与え、方向を示し、意欲をかりたて、話を聞き、説得し、そして何より共鳴を引き起こすことによってビジョンを実現していく。
ハードな技を備えているのは最低限の要件なのですが、それでは十分ではなく、感情面、ソフトな技こそが、人を動かしていくには重要であるとしています。
『優れたリーダーは、感情のレベルに働きかける』リーダーの基本的な役割は、良い雰囲気を醸成して集団を導くことである。そのためには、集団に共鳴現象を起こし、最善の資質を引き出してやることが肝要だ。リーダーシップとは、気持ちに訴える仕事なのである。あまり注目されていないが、気持ちに訴える力があるかどうかは、リーダーとしてあらゆる仕事をうまく処理できるか否かを決めてしまうほどの要素だ。だからこそ、リーダーにとってEQ (感じる知性)が重要になる。優れたリーダーシップを発揮するためにはEQが欠かせないのだ。
人の感情を理解し、そしてそれに上手に対処することが、リーダーとしてもっとも重要といってもいいスキルセットだとしています。
では、人の気持ちに訴える=「共鳴」を起こすためには、どうすればよいのか?
共鳴を引き起こすには、4つの欠かすことのできないEQ領域があり、優れたリーダーはこれらを組み合わせて、自然に共鳴を引き起こすことができる1.自己認識: 感情の自己認識、正確な自己評価、自信。自己評価を行う能力。2.自己管理: 感情のコントロール、透明性、達成意欲、イニシアチブ、楽観。自分の感情をコントロールし、ストレスに対処する能力。3. 社会的認識: 共感、組織感覚力、奉仕。共感力。4.人間関係の管理: 鼓舞激励、影響力、育成力、変革促進、紛争処理、チームワークと協調。
やはり、まずは己をできるだけ客観的に理解し、自身の感情をコントロールすること。これは、スキルだけでなく、健全な『心』、『心』の強さが基礎となる。
その上で、自分の周囲の人たちに対してもあるがままを客観的に受け容れた上で、エモーショナルな部分も含めて、対処していく。
頭で理解するのは簡単なようですが、実社会ではきわめて難しい能力ですね。でも、自己認識、他者認識は本当に大切だと考えていて、自身や人のタイプを理解するとっかかりとして、私はパーソナルアセスメントなどをよく活用しています。ストレングス・ファインダーのようなものです。できるだけ大きなサンプル数に基づいているのが望ましいですが、ネットでもあるようなゲーム感覚もあり。これでその人に対してのバイアスとはなってほしくないのですが、とっかかりとしてはとても助かるツールです。これも折りをみてご紹介しようと思います。
「共鳴」の感情をうまく方向付けてグループを目標達成に導けるかどうかは、リーダーのEQレベルにかかっている。EQの高いリーダはごく自然に共鳴を起こすことができる
優れたリーダーとなるためのスキルセット=『技』として、論理的思考、戦略思考、マネジメントスキルを土台にした上で、それに感性や構想力、影響力などのソフトな『技』が大切、さらに言うと、人間性なども備える必要がある、『心技体』という考え方に行き着く上で、もっとも大きな影響を与えてくれた書籍、私にとってバイブルといっても過言ではない書籍です。
『EQリーダーシップ』には、リーダーシップスタイルとして、6種類のスタイルがあって、リーダーは、これら6種類のリーダーシップ・スタイルを1種類、もしくは数種類採用して、状況に応じて使い分けている、という考え方も紹介しています。これもとてもとても大切な考え方なのですが、そちらはまたの機会に詳しくご紹介したいと思います。