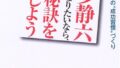前回は、本多静六さんの成功する人の仕事術や心の持ち方で、最後は、健全な体力や精神を維持するために、とにかく”歩く”という習慣をご紹介しました。
その”歩く”つながりで、最近おもしろい本を読みましたので、今日はそちらをご紹介します。
池田 光史さんの、『歩く マジで人生が変わる習慣』です。
この本では、歩くことが生活・人生に与える影響を、幅広く論文にあたりながら科学的に考察し、歩くことによる脳や身体、精神への効用、さらには社会や歴史の進化にどのように与えてきたか、そして、新たな社会的課題に対しての解決策の1つの視点も提供している、というとても興味深い一冊です。
新鮮な視点を、どんどんご紹介します。まずは、大変豊かで便利になった現代であるからこそ、より原理的(原始的?)な疑問を持つに至った背景について、
僕たちはなぜ働き、経済活動をこなしているのだろう。経済の発展は人々が豊かになっていく過程だったはずだが、少なくとも僕は、テクノロジーの進化や未来にはワクワクする一方で、活力が満たされ切れない自分と直面する日々が続いていた。それはおそらく、テクノロジーの進化の恩恵を多分に受けながら、頭と手ばかりを使うだけで済むことが増えていき、気付かぬうちに全身を使えていない日常に陥っているからじゃないか。だから取りつかれたように、奪われつつある本来の身体性を取り戻そうとするかのように、ときに山に入ったり、自然の中を歩いたり、あるいは毎日のように多摩川の河川敷を歩いているんじゃないだろうか。テクノロジーや経済の未来は、いよいよこの視点、つまり人間の身体性という視点を抜きにしては語れない時代に突入していくんじゃないか、と直感するようになった。人間の幸せは、動物として快調かどうかにかかっている。その生きた心地というものは本来、身体感覚と密接にかかわっている。それをあまりにも置き去りにした、身体性を奪ってゆくばかりの社会システムは長くは続かず、やがて綻びが生まれ、辻褄が合わなくなると思うからだ。人間の生き物としての設計は、少なくとも20万年は変わっていない。・・・・・テクノロジーの進化とパラレルに、まるでコインの裏と表のように、身体性をいかに取り戻すかが、もう1つの大きなイシューになっていくんじゃないか。それが起こるとしたらどこからなのか、そのヒントは人類の歴史を振り返ることから始まるのかもしれない、というのが好奇心の出発点だ。言い換えれば、「文明の発展とともに人類が失ってきたものは何か」ということだ。おそらくこれがー人類を人類たらしめた「直立二足歩行」ではないだろうか。
現代の科学は、本当に「歩くと脳が鍛えられる」ということを示唆しているようだ。歩行は脳を変化させる。しかも、歩行は創造性だけでなく記憶力にも影響を与える。
海馬は、歳を重ねるごとに縮んでいくことが分かっている。そのペースは概ね毎年1~2%ほどだ。こうして僕たちの脳は、ものを思い出すのが難しくなってゆく。ところが、よく歩くことで、この海馬の体積の減少ペースを抑えらえれるどころか、逆に鍛え抜かれて大きくなることが明らかになったのだ。僕たちが歩くと、その海馬で、みずみずしいニューロンが次々と誕生するのだ。僕たちの身体は、歩くことを前提にした設計を受け継いでいるーだからこそ、こうした神秘のメカニズムを経て、脳は自然と鍛えられ、健康な状態になるようにプログラムされているのかもしれない。
論文を一つ一つ、つぶさに読んでいく中で僕が感じたのは、むしろ逆のことだった。歩くと健康上、いいことが目白押しなのではない。そうではなくて、人類は「歩かなくなったから、様々な不具合が起きている」ということだ。なによりショッキングな事実は、長時間の座位が続くと、どんなに運動を増やそうとも、そのリスクを相殺するのは難しいということだ。繰り返すが、「どんなに運動を増やそうとも」である。私たちは、椅子中心の世界を設計してしまった。それは間違いだった。僕たちは、直立二足歩行を獲得し、解き放たれた手が道具を生み、文明を築き上げた。しかしその果実は、ただ僕たちを椅子に縛り付けることだったのだ。もっとも、その解決策はいたってシンプルだ。立ち上がって、歩くことである。現代人が自然に触れると、人としての本来あるべき姿に戻るのだーと。逆に言えば、僕たちは普段、どうやって脳を効率よく働かせるか、ということばかりを考えすぎているのかもしれない。実際にはそれよりも、本来はリラックスさせることのほうが求められているのだ。
おもしろい見方です。一方で、ドキッとさせられました。頭に浮かんだのが、「朝夕の通勤電車」の光景です。先を争って椅子をとりあい、何とも言えない疲れた、殺伐とした光景。。。あれが、元気のなくなった日本の象徴の絵なのではないか。。。もともとこわいなと思っていましたので、このフレーズを読んで、どこか納得してしまいました。
でも、その対策はここで提案されているように、シンプル。「歩くこと」です。
普段、人間は複雑なことを考え、頭が主導権を握っている。しかし山を歩くと全身を使い、身体優位へとシフトすることで、「日ごろ余裕のなかった頭が空っぽになるのです」。それは「脳が働く」というよりは、脳がクリアになることで、思考がスーッと整理されるということなのかもしれない。歩くことは、既存の枠にはまらない、発散的な思考力を高めることにこそ効果がある、ということになる。歩くことで、アイデアは自由に湧き出るようになります。歩行は、創造性を高めるという目標に対する、シンプルかつ強固な解決策です。
先ほど述べたように、歩くことが、考えること、創造的な思考を促すと。であるなれば、歩かないわけにはいきません。実際に、それを促すような取り組みもあるのだそうです。
シリコンバレーでは、とある工夫が、日常茶飯事のカルチャーとして半ば根付いているのだという。それが「ウォーキングミーティング」だ。ウォーキングミーティングは、創造力が高まることもさることながら、米国においては運動不足の解消という意味でも理にかなっているとみなされて浸透していったのだろう米国における肥満の社会問題化は日本の日ではない)。面白いのは、アイコンタクトも少ないために堅苦しさもなくなり、会話が弾む、という細かな事例も紹介されていたことだ。ペリシッチは、テーブルをはさんで向かい合う従来型の会議について「校長室にいるような気分になる」とも述べている。
おもしろいですね。これは私も知りませんでした。確かに、アメリカに住んでいたころは、非常に寒いところにいたので、冬はドームの中を、みんなぺちゃぺちゃおしゃべりしながら歩いたりしていました。一日の長い時間暗くなるし、鬱も多くなるし、アメリカ人はおしゃべり好きだし、おもしろい文化だなあ、なんて観察していましたが、社会性を保つことや好奇心を維持して、脳を退化させないためにも、肉体的・精神的に合理的な行動を、無意識にしていたのかもしれないですね。。。(考えすぎかも)
そして、筆者が以下の習慣を提案しています。
マジで人生が変わる:創造性を高める習慣
歩きながらアイデアを考える週に3回、40分のウォーキングを習慣化する定期的に自然の中を歩く
マジで変わる:健康を保つ習慣
座る時間をこまめに中断する食後に歩く日常的な身体の動きを増やす
これくらいでしたら、十分に実行可能なのではないでしょうか。私も、今年は、「1日10000歩」を目標にしてます。けっこう意識しないと、普通に1万歩歩けることはないので、一駅歩くとか、そんなことをしています。
ちなみに、この本は他にも、歩き方や、道具としてのシューズのことなど、他にもおもしろい論考が展開されています。たくさんになってしまうので、今日のノートには省略しますが、最後にとてもいいフレーズを紹介します。
この書籍の中で、「アルトラ」というシューズメーカーが紹介されています。背景は省略しますが、アルトラのパーパスや、バリューがとてもいいので、それを共有して今日は締めたいと思います。
「人間は、外に出ることで、内面が豊かになります。自然の中で過ごす時間が増えれば増えるほど、人は健康的に、そして幸せになれる。そしてそれが、アルトラの全てのシューズに込めた想いです」自分自身と周囲の世界をより深く知るために、動こう