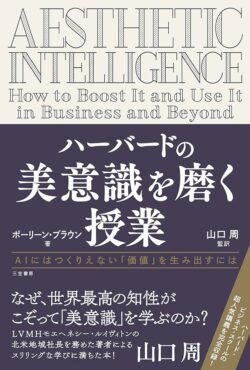私はリーダーシップ能力を磨いていくにあたり、新しいスキル=『技』をどんどん学んでいくことからはじめました。特に私は文科系の出身であったため、「世界に売れる、自分ならではの技は大学時代に何を身に着けた?」と考えたときに、違いを作れる何かを持っているわけではないと考えるようになりましたし、コンサルのようなビジネススキルがOJTでばんばん身につくような仕事をしていたわけでもないですし、のちにヘルスケアを基盤として生きていくと決めたもののサイエンスの知識の基盤があったわけでもないことから、ビジネスの世界で一人前になるためには1つでも多くの「ハードな技」を身に着けよう、とやっきになっていました。ふりかえれば、コンプレックスとあせり、だったのですね。
経営、ファイナンス、マーケティング。。。とにかくたくさん勉強しましたし、そのおかげで“基本の型”は十分に身についたと思います。その後、経験も重ねましたので、周りと違いを作るために、意図的に基本のフレームワークからはなれて、自分なりのユニークさを出そうとも努力してきました。『守破離』の「破」です。おかげで、ちょっとしたユニークさは出せるようになってきたのかなと思ってます(自分としては)。
そうした過程を経て今重視しているのは、『直観』『感性』です。左脳ではなく、右脳に刺さる“何か”。ロジックとかデータとかサイエンスに非常にこだわって仕事をしてきた中で、“ひらめき”のような感覚的な部分が、結局正しいと思えることが多くなったこと、いろいろなタイプの顧客に接し、いろいろな人たちと仕事をしてきた中で、人を動かしているのは「感情」的な部分も大きいなと思ったこと。
EQの大切さ、ですね。そんな中で、リーダーの素養として、最近は「アート」の部分も高めることが注目されてきています。そこで、今日はポーリーン・ブラウン 著 『ハーバードの美意識を磨く授業』 をご紹介します。
この書籍は、ハーバード・ビジネス・スクールでの人気講義を基に書籍化されたもので、ビジネスにおいて、AIやデータ分析では補えない人間ならではの感性、「美意識」の重要性を訴えている書籍です。
まず、カギとなる論点として、以下を述べています。
美意識は大切である。そして現在、美意識はこれまで以上に必要とされている。美意識に根差して企業を構築し、成功に導くのは、審美眼に富む人たちである。人は、自分が思う以上に、美意識を備えている。しかし、筋力と同じように、鍛えなくてはならない。美意識をうまく活用できれば、ビジネスを進化させ、さらにはビジネスを改革することもできる。
企業経営、ひいてはリーダーとしての素養として、「美意識」が大切である、としています。
では、「美意識」とは何か?
本書で使う「美意識」という言葉は、人が自ら感覚を通じて対象や経験を理解し、知覚することで得られる喜びや満足感のことだ。そして、後述するが、美的知性とは、ある物事や経験から引き起こされた感覚・感情に気付き、それを洞察力を持って解釈し、わかりやすく表現する能力のことだ。美意識に支えられたビジネスであれば、消費者が「喜んで買いたい、消費したい」と思うような製品やサービスと提供できる。消費者は、そうした製品やサービスの「利便性」に対してではなく、見た目、味、香りや音、手触りといった「感覚上の満足」に対して、快く高い料金を支払うのだ。私はこの「美意識をビジネスに活かす」という極めて重要なスキルを美的知性、あるいやAesthetic intelligence の頭文字をとって「第二のAI」と呼んでいる。美意識を磨いていく際に重要になるポイントの一つが、「美的共感」と私が名付けた概念だ。「第二のAI」は、自身の美的感覚を育むことから始まる。しかしその一方で、たとえ自身の感性と違っていたとしても、他の人々の感性が市場の動向をよりよく反映している限りにおいては、彼らの感性や感受性を深く理解し、尊重することが求められる。
もともとはコンサルとして「左脳」の世界で生きていた著書が、どうして「美意識」を重視するようになったのか?
ペンシルバニア大学ウォートン校を卒業して数年たった時、私はエスティローダー・カンパニーズの戦略を策定、提案するチーフ・ストラテジストに任命された。同社にコンサルティング会社のベイン・アンド・カンパニーから転職した私は、この不慣れな企業での新たな仕事に、「ベイン式ツールボックス」を持ち込んだ。・・・・ところが、フレッドは、私のベイン流の報告書を机にたたきつけ、射貫くような、青い目で私を見た(すべてお見通しだったのだろう)。なんということだ。フレッドは、私の積み上げた報告書には、全く興味を示さなかった。報告者は過去の実績を分析していただけで、画期的なアイデアや前向きな解決策はなんら提示していなかったのだ。今すぐ実行に移せる具体的な提案など、一つもなかった。フレッドが私に期待したのは、ビジネスをものにすることーつまり、顧客に提供するべき価値を真に理解し、的確に認識し、大切にすることであり、単に合理的・客観的に観察することではなかった。私が会社の価値を高めることができるとすれば、その唯一の方法は、戦略をうんぬんするのではなく、自ら化粧品部門の業務に没頭し、ショッピング・フロアで時間を過ごし、顧客の購入の動機や願いや夢を理解することだ、とフレッドはわかっていたのだ。それは、私が自分自身と向き合い、従業員としてではなく一個人として、「自分らしさ」を仕事で発揮するということでもあった。エスティローダーが何よりも必要としていたのは、より綿密な財務モデルではなく、美容化粧品を買い、使うことを純粋に楽しむ人の「心の奥底にあるもの」を見抜く力だった。
アヴェダ買収のプロセスは私にとって、多くのことに気づく機会となった。顧客がアヴェダを愛したのは、その配合成分の質が良いからだけではない。アヴェダが優しさにあふれ博愛主義的な使命感を持っているからでもあった。そうしたアヴェダの使命感は、環境に優しいパッケージのデザインにも、天然素材を使用したアヴェダのサロン、さらにはラベンダーやローズマリーミントといった天然成分の香りにも反映されていた。もしも、私がアヴェダの財務実績の分析結果だけに注目していたなら、はるかに重要なこと、つまり、顧客は製品に効用や価格以上のものを望んでいるという事実を、見逃してしまっていただろう。実際のところ顧客は、自分と自然を再び結び付けてくれる製品、そしてごく日常的な作業さえも「体験」に変えてくれる製品を求めていたのだ。
顧客をまっさらな目で見て、感じる。立場が上がるほど、より顧客を見る目を失ってはいけない。非常に刺さった部分です。顧客から選ばれるためには、虚心坦懐に、顧客の感性に働きかけるということですね。
消費者の心を動かすものとは、いったい何だろう?それは、とても根本的なもの、例えば、石鹸とリラクゼーション、カシミアと温もり、クラシック音楽と安らぎ、アイスクリームと快楽といった、人と物との感覚的なつながりではないだろうか。「いい買い物ができてよかった」という体験には、美意識を語る時の基本言語となる「五感」が大きく関わってくる。味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚がどのように機能しているかを知ること、つまり五感が互いにどう影響しあい、マーケターがどのように顧客の五感に刺激を与えているかを知ることは、効果的・究極的に言葉を使うため、そして企業が競争優位を確立、維持していくための鍵となる。研究が示すところによれば、消費者が感じる喜びや高揚感のうち50パーセントは、期待感と記憶に関連し(過去の感覚体験の残留効果)、残りの50パーセントは、購入時の直接体験(その瞬間に働いた五感の効果)に関連しているという。私はこれを、ハロー効果と呼んでいる。私がここでいうハロー効果とは、いわゆる「後光効果」の意味ではない。体験や経験とは、実際に経験する前に感じる期待感、実際の体験や経験、そして経験の記憶というパーツを連ねたものだということ、そしてその一連の流れが、次の新しい経験につながる、ということだ。
そして、企業としての問題解決を図るためにも、「美意識」が必要であると。
企業の成長や存続を妨げる要因に立ち向かうための最善策をご紹介しよう。私が「美意識に基づいた問題解決」と呼ぶものだ。一般的に、ビジネスにおける典型的な課題の解決策は、ビジネス・スクールのケース・スタディやベストセラーのビジネス書の中には見つからない。つまり、高度に系統立てられたフレームワークや分析ツール、市場に対する冷静な見解の中には解決策はないということだ。顧客への深く共感的な理解(彼らは「何を、どの店で買っているか」と考えるのではなく、「どう感じ、何にときめいているのか」と考えること)、そして「どうすれば、顧客にもっと喜んでもらえるか」という洞察の中にこそ、課題解決への答えは見つかる。つまるところ、物を買うのは、機械ではなく、人間なのだ。人間は感情的な生き物だし、「それを買ったら、どんな気分になるか」で買うかどうかを決める。そして、手に入れた後の感動が大きければ大きいほど、その製品やブランドにますます魅了され、愛着を深める。市場を注意深く見まわしてみると、多くの企業リーダーが、一緒に働く人たちや顧客との人間的な結びつきをおろそかにしすぎている、と私には思える。人間的な結びつきを失えば、企業は存在意義を失う。そのような企業が顧客のニーズになんとかこたえようとしているとしても、もはや顧客に「喜び」をもたらしていないのは確かだろう。企業は生き残るために、原点に立ち返るべきだ。製品やサービスに再び人間らしさを加える必要がある。食品業界やエネルギー業界など、ごく一部を除き、世の中に出回っているものの大半は必需品ではないことを忘れてはならない。人はこれ以上の「がらくた」を必要としていない。それどころか、多くの人たちが「がらくた」を減らし、生活を簡素化しようとする時代を迎えている。この流れは当面、止まらないだろう。
企業が成長するためには資産価値だけでなく、美的価値を高めなければならない。美しいものを作り出し、人々の感性を刺激し、気持ちを高揚させ、関係を築き上げる手腕や能力のある企業や人々が、最後には勝利する。問題の解決にあたる時に問うべきは「他社の解決策は何か」ではなく「今、自社が直面している問題について、私たちの美意識や価値観を反映した解決方法は何か」である。
その「美意識」を伝える上で、「言語化」することは大切であるとしています。感性部分が多かった中で、これはハードな面での技といえますね。
「表現力(アーティキュレーション)」が不可欠だ。何か新しいことを理解し受容してもらおうとする時、鍵となるのが「言葉にする力」なのだ。表現力(アーティキュレーション)とは、美意識に基づいた戦略、究極的な目標、理想を、言葉やストーリーテリング、その他のコミュニケーション手段を使って、明確に、爽やかに、歯切れよく伝える力のことだ。美意識の感じられるマーケティングやメッセージングも、そこに含まれる。
テクノロジーが劇的に進化していく中で、人間ならではの能力を研ぎ澄ます必要があると。
私たちは、二つの世界で暮らしている。そう実感することが次第に多くなってきた。一つは、オートメーション、アルゴリズム、人工知能によって支配される世界。もう一つは、人間同士のふれあい、感情的な結びつき、特別に設計された自分だけの体験を追求する世界だ。こうした世界の二極化は美意識に影響を与え、そして美意識もまた進化し続ける。今後も、文化や人口構造が変化するにつれ、私たちが美しいと感じるものや喜ばしいと思うもの、あるいはつまらないと思うもの、不快だと拒絶するものも同様に変わっていく。ソーシャルメディアの躍進を見ればわかるように、人間はこれからも、人と人との関係(relationship)、体験(experience)、思い出(memory)に重きを置くだろう(私はこの3つをまとめてREMと呼んでいる)。
私は、『技』の基礎としてハードなスキルセットも依然としてとても大切だと考えています。その地盤の上で、ソフトなスキルセットも鍛錬する必要がある。それはテクノロジーが人間のハードなスキル部分を瞬時にまかなってくれるようになるこれからだからこそ、リーダーシップを鍛錬するにあたり、アートな面にもさらに焦点があたっていくのだろうと思います。