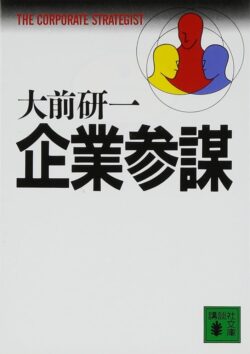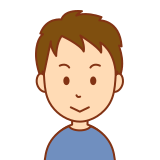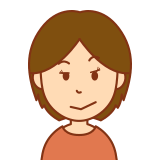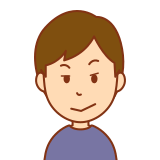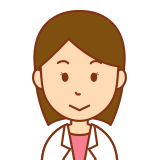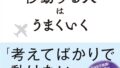「基本の型」を身に着けるための書籍として、前回は、バーバラ・ミントの『考える技術・書く技術』をご紹介しましたが、今回も同様に社会人となったからと言わず、学生時代からの教育の一環としての思考法として身に着けるべき“問題解決力”、それを身に着けるために絶対に学ぶべき一冊として、大前研一氏の『企業参謀』をご紹介します。
本書は、戦略的思考をテーマにした、企業経営や問題解決における実践的なアプローチについて、“勘”ではなくいかに科学的な方法で解決していくかが紹介された、名著中の名著です。ご覧になった方も多いと思います。
問題解決力をテーマにした手法や書籍は数多く出版され、今や広く浸透していっていますが、どれもそのルーツはこの書籍で紹介された手法に集約されるのではないかと思います。私にとっても教科書ですし、大前氏は私が勝手に尊敬する先生のお1人です。
今さらではありますが、私が個人的に大切だと思う基礎的な考えたについて、いくつか共有します。
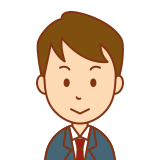
戦略的思考の第一段階が、ものの本質を考えるということにある・・・・・スタート時点で大切なことは次の一点であろう。
「設問のしかたを解決志向的に行うこと」
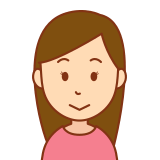
設問を解決策思考的型にすることによって、物の本質に迫る解決案というものを出す場合、設問が的を得ているためには、問題点そのものがすでに正しく把握されている必要がある。・・・・
「問題点の絞り方を現象追随的に行うこと」
「正しい問いの設定」
問題解決のプロセスにおいて、これが成功の半分を占めると言って過言ではないですね。それに迫るための科学的なアプローチとして、イシュー・ツリーやプロフィット・ツリーなど、構造化してMECEで現象を分解して把握するアプローチ(昨日のバーバラ・ミントの方法と同じです)が必要であると。この書籍の初版が1975年ですから、50年前の考え方がいまだに基礎となっている。革命的です。
そして、参謀としての心構えとして、「参謀五戒」として、以下を列記します。
戒1=参謀たるもの「イフ」という言葉に対する本能的恐れを捨てよ
戒2=参謀たるもの完全主義を捨てよ
戒3=KFSについては徹底的に挑戦せよ
戒4=制約条件に制約されるな
戒5=記憶に頼らず分析を
今でも参謀ばかりか、リーダーシップ能力を身に着けるあたっての基礎的なマインドセットですね。それどころか、AIによって左脳的思考過程が代替されるこれからは、またこれまでと違った形で問題解決をしていく必要があり、実行~ふりかえり~また実行~ して行動するためにも、必要なマインドセットではないかと思います。
そして、企業経営には、ヒト・モノ・カネ・情報、多くの要素が複雑に絡み合って、成長・存続の道を希求しているわけですが、以下の考え方は、今も基本として身に着けておくべき素養ではないかと思います。
私はすべての経営的問題は製品・市場戦略にその根源と解決の緒を見つけることができると信じている。
製品・市場戦略は、最終的には美しい一つの文章として記述できるところまで昇華しなくては、本当の味わいが出てこない。その文章は、
①世の中の動きと構成に対し、自社がどのように対処してきたか、
②今後この趨勢が続けばどのようになるか、
③これを抜本的に変革させるにはどのような打つ手があるか、
④自社の得手・不得手、強さ・弱さ、緊急度などを勘案し、どの打つ手が現状に最も適しているか、
⑤例えばその打つ手が失敗したとき、どのように対処したらよいか、
⑥実施後の期待効果はどのようなものであるか、
⑦誰が、いつ、どのようなプログラムを実行すれば全体として所期の成果が上がるか、
という順序で展開されているだろう。
私は、これが基本のアプローチとして、考えてその経験を積み重ねてきましたので、今でもクイックに状況整理と仮の戦略立案をする際はこの流れで考えますし、短時間でも大外れすることなく、それなりの筋の考え方をすることができるようになりました。
逆に考えると、このアプローチに従えば、“誰でも”それなりのプランはできるわけで、しかも今後はAIが瞬時に生成してしまうとなると、“どうやって違いを作るか”が今はもっと大切なわけですが、それについてもまた追ってご紹介したいと思います。
戦略とは、競争相手との差別化、簡単に言うと「違いを作って、ケンカに勝つ」ことだと私は考えていますが、それを実現するためにこの書籍の中でも、“KFSにこだわる”ことや、いくつかの軸が紹介されていますが、最後に1つ、私に大きく影響したコンセプト
戦略的自由度
について、ご紹介します。
改善というものは、すべての方向を持っているのではなく、「異方性」によって特徴づけられている。もちろん経営資源が無限にあれば、何もかも改善につぐ改善を加えればよいのであろうが、戦略的な改善というものには、少なくとも私の経験では、著しい異方性がある。先に述べたKFSに基づく戦略が、事業のスウィート・スポットを見つけることであったとすれば、本項で述べる戦略的自由度の話は、そのスウィート・スポットのまわりにどのくらい戦略的打ち手の自由度があるか、という話である。
現実的に見て、戦略を立案すべき方向の数のことを「戦略的自由度」と呼ぶ。
戦略的自由度を規定し、その自由度のある軸に沿って徹底的に追及してゆくという方法をとれば、きわめて短期間に、それこそ処理できないほどの戦略的アイデアがわいてくるのである。
詳細のフローは割愛しますが、私もこの考え方でアイデアが出るようになりました(方法が正しいかどうかはおいておいて)。何もフレームがない中でブレストするより、考える軸を作ることによって、考える要素が明確になって、アイデアを絞りだしやすくなると思いますし、これは色々な分野に応用できる考え方かと思います。
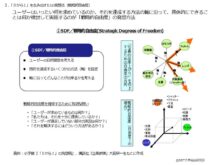
出所:BBT
そして、最後、これも今もおなじだなと思う記述を持って、今回を締めたいと思います。
「原則に忠実」を忘れるな・・・順風満帆に進んでいるかに見えた会社が急におかしくなることがよくある。こうして「立志伝中の人」が「落ちた偶像」になるのは、自分の事業基盤であった大原則をわあ擦れて動き出す場合が多い。先見性のある経営者なら、自分はどのような顧客のために、どのようなサービスを提供し、どのようなメカニズムで収益を上げているのか、ということを寸時も忘れることはしないだろう。
リーダーシップを目指すうえで、「何に志を持つか」、その原点を忘れずに精進していくことが大切ですね。